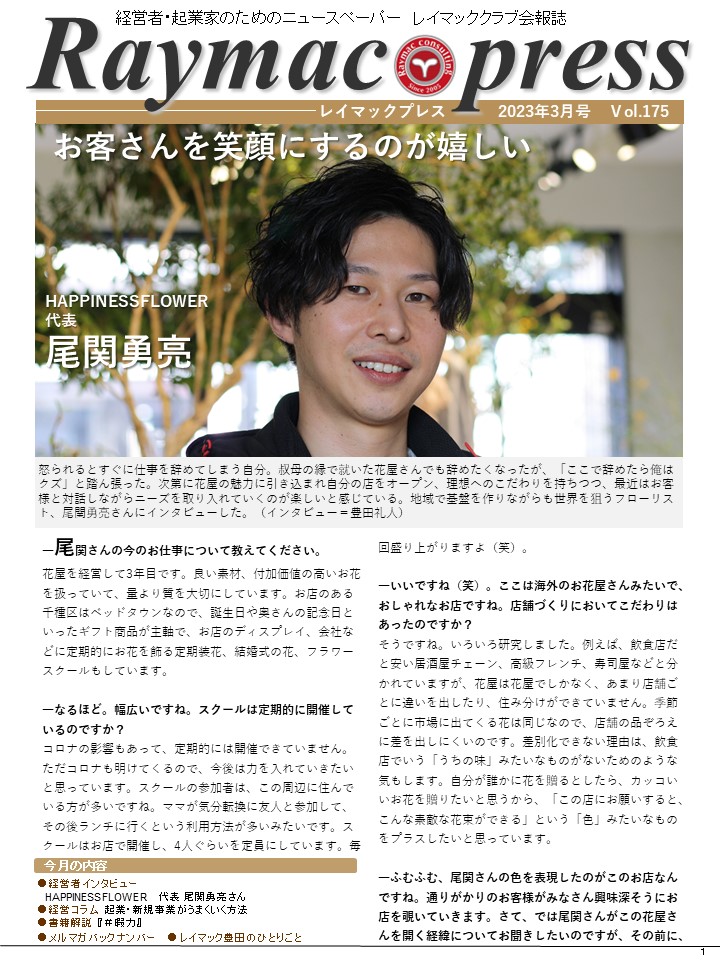2010/08/09
ナビタイムのフリーミアムモデル
経路検索サービスで急成長するナビタイムジャパン 。
この企業の収益源は大きく2つ。
1つは広告収入。地図上に飲食店などの情報を載せる販促サービスです。
例えば、名古屋駅付近でイタリアンを食べたいと思った人が検索すると、ナビタイムに広告出稿したイタリア料理店が検索表示されます。地図情報も同時に表示 されるので、その人はそのお店に行く動機を高めます。新規客を獲得できるお店などはメリットを感じ、広告料を払う―――。
もう1つは有料会員から得られる収入。
ナビタイムでは、無料でもサービスを利用できます。例えば、簡単な経路検索などは無料です。
しかし、トータルナビと呼ばれる、徒歩ルートや最寄り駅の出入り口番号、何両目に乗るのが便利か、などの細かいナビ情報は、有料会員にならないと利用できません。そこで無料利用者と差を付けています。ちなみに料金は月210円~。
ナビタイムの有料会員は420万人で、同社のサービス利用者全体の10%に当たるそうです。逆に、90%は無料版利用者ということ。
つまり、90%の無料利用者にかかるコストを10%の有料会員でまかなうモデルです。
ベストセラー「FREE(フリー)」では、このモデルをフリーミアムと読んでいます。同書では、5%の有料ユーザーが残りの無料ユーザーを支える「5%ルール」を紹介していますが、ナビタイムの場合はそれが10%というわけです。
広告モデルとフレーミアムモデル。
どちらも、フリーを活用してビジネスを成長させる代表的なやり方です。
これからの時代、フリーについては多少なりとも中小事業者も考えていかなければなりません。
もちろん僕自身の事業でも参考になることがたくさんありそうです。
●追伸
8月18日、18時30分よりウインクあいちでセミナーを行ないます。愛P勉強会の第9回目です。今回のテーマは「誰でも分かる財務脳トレーニング」と 題して、ややこやしい財務やお金の話を、できるだけ分かり易くお届けしようと思っています。まったりと勉強したい方、どうぞ起こしください。→申込みはこちらから
●愛される会社になるための経営ネタ、ビジネスモデルネタ、マーケティングネタを提供する無料メルマガ
『愛される会社の法則」 も合わせてお読み頂けると嬉しいです。読者の声はこちらから。
2010/08/07
コメント力を上げる方法
今日は、クライアントである印刷会社さんの経営方針発表会に出席しました。
ここでは、社長が基本方針を掲げた後、社員さんたちが1年の活動を報告し合ったり、これからの1年間に何を重点的に取り組むのかを発表します。
この発表会で、「講評」をして欲しいと頼まれていました。つまり、コメントして欲しい、と。
実は、あんまりコメントするのって得意ではないので、昔買って読んだこの本を本棚から引っ張り出しました。↓
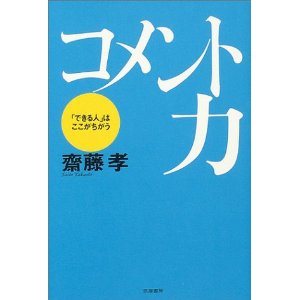
明大教授でテレビでもおなじみの斉藤孝さんが2004年に出した本です。
コメント力について色々と書いてあるのですが、アレもコレもできないので、一点に集中して行なうことにしました。
それは、優れたコメントとは、発表者がどこにエネルギーを注いだのかを理解し、それについて感想を述べること という点です。
発表者がエネルギーを注いだ部分は、その人にとってもっとも重要なことのはずです。そこについてコメントすることで本人は認められたと感じてくれます。
また、聞いている人たちも、発表者が言いたいポイントを再度確認できるので理解が深まります。
実際にやってみると、これが結構うまくいきました。
社長から頂いた言葉から察すると、なんとか満足していただけるコメントができたのかな、と思います。
本から得た知識を即実行し、すぐに効果が出ると、とっても得した感じがしますね。
充実した気分を味わいながら、帰途につきました。
●愛される会社になるための経営ネタ、ビジネスモデルネタ、マーケティングネタを提供する無料メルマガ
『愛される会社の法則」 も合わせてお読み頂けると嬉しいです。読者の声はこちらから。
2010/08/06
ニュースレターの嬉しい効果
今日も午前中はある銀行の方と会っていました。
以前面識があった方は転勤されていなかったのですが、後任の方も僕が毎月送っていたニュースレターを読んでいてくれて、「あ、レイマックの豊田さんですね」と知っていてくれました。
こうなると、断然話は早いです。
初対面なのに、先方は僕のことを既に知っていてくれるわけだから、すぐに親密な空気が出来上がります。僕の企画も興味深く聞いて頂き、質問されっぱなしでした。
やっぱり、ニュースレターって、効くよな・・と思いました。
人間が毎月動いて面会に行くとコストはかかるし、お互いちょっと重たいですよね。それを低コストで紙が代行してくれるのですからやらない手はありません。
そんなわけで、ますます頑張ろう!と決意を固くしたのです。
ツイッター、ブログ、フェイスブックなど、WEB上のコミュニケーションツール全盛ですが、こういったツールではアクセスできない層が存在します。
アナログツールとデジタルツールの使い分け、併用が必要なんだ、と思います。
●追伸
8月18日、18時30分よりウインクあいちでセミナーを行ないます。愛P勉強会の第9回目です。今回のテーマは「誰でも分かる財務脳トレーニング」と題して、ややこやしい財務やお金の話を、できるだけ分かり易くお届けしようと思っています。→申込みはこちらから
●愛される会社になるための経営ネタ、ビジネスモデルネタ、マーケティングネタを提供する無料メルマガ
『愛される会社の法則」 も合わせてお読み頂けると嬉しいです。読者の声はこちらから。
2010/08/05
早朝コンサル、そして銀行でプレゼン。その後、再びコンサル。
今日は、愛P の会員さんと早朝ミーティング&コンサル。
この会員さん、とても熱心に仕事に取り組むので、どんどん成果が出ています。会社としての業績も好調で、今後がとても楽しみです。僕の成功は、クライアン トさんが成功すること。クライアントさんがもっと成功できるように、今後もしっかりやっていきたいと思います。これからもよろしくお願いします!
その後、自転車である金融機関へ。支店長と会って、こちらのプランを提案。好感触。いっしょにコラボできればいいなと思います。今週金融機関の支店長と会 うのは2人目です。実は、明日も別の銀行の支店長と会う予定です。中小企業様の業績アップのために協力し合えればと思います。
これから夕方にかけては、印刷会社さんへ行って、コンサルティング。社長&営業スタッフさんたちと打合せをする予定です。
帰ってきたら、メルマガ書いて、明日の準備して・・・。
暑いけど、頑張ります!!
●追伸
8月18日、18時30分よりウインクあいちでセミナーを行ないます。愛P勉強会の第9回目です。今回のテーマは「誰でも分かる財務脳トレーニング」と題して、ややこやしい財務やお金の話を、できるだけ分かり易くお届けしようと思っています。→申込みはこちらから
●愛される会社になるための経営ネタ、ビジネスモデルネタ、マーケティングネタを提供するメルマガ
『愛される会社の法則」 も合わせてお読み頂けると嬉しいです。
2010/08/04
「疲れた」ではなく「ダイエットになった」を選択しよう
「ダイエット」とか「健康」というキーワードを自分の中に持っているといいですよね。
例えば、これだけ暑いと外を歩くのもイヤになるのですが、「ダイエットになる」と思えば前向きに歩けます笑。
道を間違えて余計な距離を歩くことになってしまった時、「オレはなんて段取りが悪いんだ!」と自分を責めるより、「普段よりたくさん歩いたので、健康に良かった」と考えた方が、さらに健康に良いですよね。
他にも、営業マンにしつこく営業された時、「ウザイな~」と考えるより、「どうやってプレゼンするのかな」と興味を持って対応すれば、自分にプラスになります。
要は、事実に対して、どういう考え方を選択するか、という問題。
仕事で失敗して、「私はダメなヤツだ」と落込むのか、「いい経験ができた」と前向きに考えるのか、どちらを選択するのかは、自由なのです。
楽天の三木谷さんは起業当初、1ヶ月走り回って数件しか出店者を集められなかった時、「頑張ったのにこれだけしか集らなかった」という考え方ではなく、「数は少ないが出店してくれる人がいた。このビジネスは絶対いける!」と思ったそうです。
事実に対してどういう考え方を選択するのか?
普段の生活からいろいろと試せますよね。
●追伸
子供がトランスフォーマーにどっぷりハマっています。大人から見てもカッコイイ。さすがタカラトミー。
●愛される会社になるための経営ネタ、ビジネスモデルネタ、マーケティングネタを提供するメルマガ
『愛される会社の法則」 も合わせてお読み頂けると嬉しいです。
最近のブログentries
コンサルプランconsulting plan
情報発信information