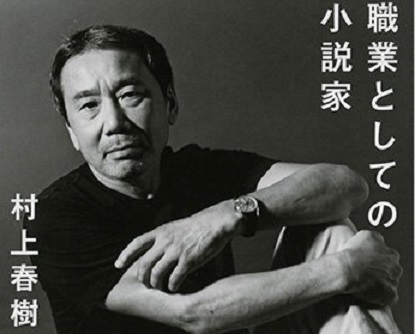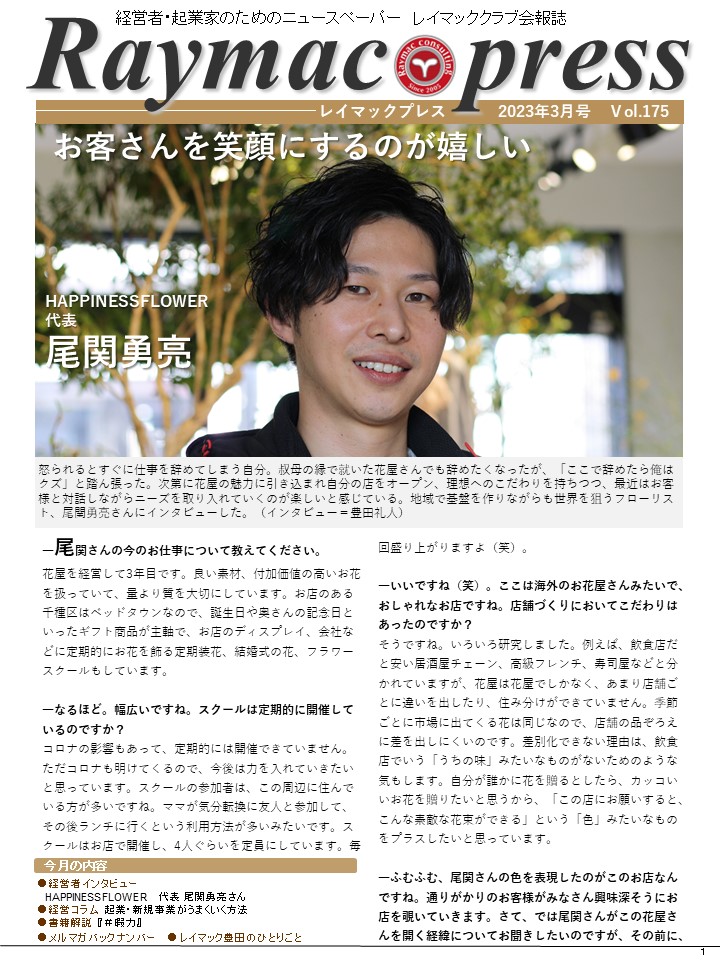2017/11/10
うまくいっていることにフォーカスする。
愛知県名古屋市で中小企業の売上増加を支援する経営コンサルティング事務所、レイマックの豊田礼人です。
■悪い話といい話
うまくいかないことを嘆くことよりも、うまくいっていることに焦点を当て、そこをしっかり評価するということは大切です。
先日会った経営者は、最近、あまりいいことがないと渋い顔をして現れました。
売上面で厳しい状態が続いていること、お客様とのちょっとしたトラブル、社員採用が進まないことなどなど・・・。
しかし、その話の中で、新たな販売の軸となるパートナーと出会ったことも出てきました。
「それ、いい話じゃないですか」
と僕が伝えると、はっとした顔して、
「そうですね。言われてみれば、これは未来につながるいい話ですね」
と笑顔になりました。
こちらもつられて笑顔になりました。
■暗いニュースの洪水
テレビをつけると、悪いニュースばかりが流されています。
殺人、自殺、テロ、交通事故、暴力、汚職、詐欺、不景気、いじめ・・・。
連日連夜、これでもかというくらい次から次へと暗いニュースが届けられます。(頼んでもいないのに)
こういうニュースの洪水の中にいるとなんて暗い世の中なんだ、と思ってしまいます。
しかし、実は世の中には明るいニュースや楽しい話だって、たくさんあります。それがニュース番組では報道されないだけです。
日本にはいいことやうまくいっていることがたくさんある。世の中、捨てたもんじゃない。
暗い部分ばかりを見るのではなく、明るい部分も見れば、もっと晴れやかな気分で毎日をすごせるはずです。
■うまくいっていることに焦点を当てる
企業のコンサルティングをするとき、経営者や社員さんにヒアリングをします。
その際、企業によっては、これでもかというくらい会社の悪い面が社員さんから出てくる場合があります。
小さなことから大きなことまでさまざま。それを聞いているとこちらの気分が滅入ってしまうこともありますが、貴重な意見としてなるべく真摯に受け止めます。
一方で、会社の良い点やうまくいっていることについては、あまり出て来ません。まずは不満が優先的にどんどん出てくるんですね。仕方のないことかもしれませんが、とても残念な気持ちになります。
うまくいっている点もたくさんあるからこそ、会社がここまでやってこれたという事実もあるわけです。そこにもっとフォーカスして、前向きな気持ちで仕事に取り組めたら、結果も変わってくると思います。
■自分レベルの視点で
自分レベルではいかがでしょうか?
僕たちは、自分のうまくいっている部分に目を向け、それをしっかりと評価しているでしょうか。
出来ていないことばかりを指摘し、自分を責め、無意味に落ち込んだりしていないでしょうか。
あるいは、上司や部下や同僚や家族に対して、そういう目で見ていないでしょうか。
うまくいっていないことを反省し、その改善に取り組むことはもちろん必要。それがないとただの高慢な人になってしまう。
そのうえで、うまくいっていることを評価し、その達成をかみしめ、次へ向かう活力にしていきたい。
ここまではうまくいっている。さらに良くするためにはどうすればいいか?を考えよう。
それが自分の推進力。
応援しています。
(無料メールマガジン「愛される会社の法則」第606号より)
※メルマガの登録はこちらから。(無料)
【第46回セミナーのお知らせ】———————————————-
11月14日にセミナーを行います。テーマは「あなたのコンサル化」です。
(内容)
モノを売ろうとする姿勢だけが強いと、かえって全く売れないという事態に陥ります。
そうではなく、小さな会社は、顧客が抱えている困りごとやニーズを把握し、その解決をサポートするという姿勢がとても重要です。信頼できる「コンサルタント」となり、顧客の問題解決のために、自分の専門知識と人間性をフル投入していく、というセルフイメージを持つのです。
今回のセミナーは、小さい会社が「コンサルタント」として顧客をサポートするためのスキルや考え方を分かりやすく解説し、すぐに実行に移せるようなアイデアを提供いたします。
【日時】 :2017年11月14日(火) 19時~20時45分(18時半受付開始)
【場所】 :ウインクあいち 904 名古屋市中村区名駅4-4-38
【料金】 :5000円(税込み)レイマッククラブ会員は2000円
※友割あり(ペアで参加されますと、各お客様1000円オフ。但し初参加の方のみ
【定員】 :30名
【懇親会】:あります。予算別途3000円くらいです。
お申込みは→: https://raymac.jp/46thseminar/
2017/11/07
ZOZOTOWNとレディオヘッド
ZOZOTOWNが10月1日から、購入者が送料を決定できる「送料自由」の取り組みを試験的に実施しました。
その結果、「送料0円」を選択したのは全体の43%、平均送料は96円だったそうです。利用額や頻度が高いユーザーほど送料を有料にする傾向があったとしています。(ITmedia ビジネスオンラインより)
そしてZOZOは、11月1日から、全て一律で送料200円にする、と発表しました。
この事例のように、消費者が商品の代金を決めて、自由な金額を払う方法を「ペイ・アズ・ユー・ウィッシュ方式」と呼び、「スマート・プライシング」という本に詳しく書かれています。
Pay as you wish.
つまり、あなたの好きなだけ払ってください、ということ。
「スマート・プライシング」には、レディオヘッドというロックバンドが、自分たちの10曲入りアルバムを「ペイ・アズ・ユー・ウィッシュ方式」でダウンロード販売した事例が紹介されています。
それによると、180万人以上の人がこのアルバムをダウンロードし、うち40%の人がいくらかのお金を払い、60%の人が全く支払わなかったそうです。ある調査では平均は2.26ドルだったそうです。それでも、レコード会社を通してCDを発売するよりも多くの利益をバンド側は得たとされています。
そして、このことが大きなニュースとなり、その後に発売したCDの宣伝効果としては十二分の成果を上げた、という後日談もあったそうです。
ロック・バンドの「楽曲ダウンロード代」とアパレルのネット販売における「送料」という、全く異なるものですが、全体の40~60%の人は全く払わない人がいるんですね。しかも平均すると通常価格よりもだいぶ低くなっている・・・。
自分が何かの価値を得る時は、それを提供してくれた人に対価を払うのが当たり前ですけど、そういう風には考えない人が半分くらいいるのだとすると、ちょっと寂しい気もします。
ZOZOを運営するスタートトゥデイの前澤社長も「送料は基本的に有料であり、無料で届くわけがないと社会的に認知してもらいたい。」と言っているとおり、運送会社のドライバーさんが動いているからこそモノが届くわけで、その対価を払って当然です。
田舎の方に行くと、無人の野菜販売所がありますが、あれなんかも払わずに持って行く人が半分くらいはいるのでしょうか。だとしたら残念です。
「スマート・プライシング」では、ロンドンの「ジャスト・アラウンド・コーナー」という高級レストランが20年以上前から「ペイ・アズ・ユー・ウィッシュ方式」で営業していて、成功していると報告しています。このお店のオーナーは「おいしい食事とすばらしいサービスを提供した時、お客はいつもよりチップをはずんでくれる。だから決めたんだ。料理にいくら払うかもお客に任せようってね」と言っているそうです。
このレストランと、ZOZOの送料及びロックバンドの楽曲ダウンロードとの違いは、対面で支払うかネット上で支払うか、の違いがあります。やはり顔が見えないネット上では、払わずに済ましてしまう人の割合が増えるんですかね。
誰にも見られていない時にこそ、人間の本性が現れる。他人は見ていなくとも、神様は見ている。
受け取る価値に対して、誠実に支払いたいと思います。
【第46回セミナーのお知らせ】———————————————-
11月14日にセミナーを行います。テーマは「あなたのコンサル化」です。
(内容)
モノを売ろうとする姿勢だけが強いと、かえって全く売れないという事態に陥ります。
そうではなく、小さな会社は、顧客が抱えている困りごとやニーズを把握し、その解決をサポートするという姿勢がとても重要です。信頼できる「コンサルタント」となり、顧客の問題解決のために、自分の専門知識と人間性をフル投入していく、というセルフイメージを持つのです。
今回のセミナーは、小さい会社が「コンサルタント」として顧客をサポートするためのスキルや考え方を分かりやすく解説し、すぐに実行に移せるようなアイデアを提供いたします。
【日時】 :2017年11月14日(火) 19時~20時45分(18時半受付開始)
【場所】 :ウインクあいち 904 名古屋市中村区名駅4-4-38
【料金】 :5000円(税込み)レイマッククラブ会員は2000円
※友割あり(ペアで参加されますと、各お客様1000円オフ。但し初参加の方のみ
【定員】 :30名
【懇親会】:あります。予算別途3000円くらいです。
お申込みは→: https://raymac.jp/46thseminar/
2017/11/04
今週の振り返り。飲みコンサルとか、アクアイグニスとか、実家とか。
愛知県名古屋市で中小企業のNew(新しいチャレンジ)を支援する経営コンサルティング事務所、レイマックの豊田礼人です。
今週もあと数時間で終わります。今週も色んな人に会い、色んなことを考えました。振り返ってみます。
29日の日曜日は大雨。風邪気味で控えていたプールを再開。ノルマの1000メートルを泳ぎました。帰りにワイン買って、夜は家族でたこ焼きパーティ。たこ焼き大好き。
月曜日は公的仕事。コンサルタントにコンサルティングするというお仕事でした。
夜は、クライアントの経営者と「飲みコンサルティング(通称飲みコン)」。これは、1~2か月に一度、美味しい食事とお酒を頂きながら、経営者としての悩みを相談してもらったり、私がアドバイスをしたりする仕事です。今回はタワーズの懐石料理屋の個室で上品な食事とお酒を頂いた後、場所を居酒屋に移し、いつもの感じで飲み直し。いい時間が過ごせました。
火曜日は午前中はブログなどを書いた後、春日井に移動。和菓子屋さん、洋食屋さん、お蕎麦屋さんを立て続けに訪問しコンサルティング。皆さん意欲的ですが、特に和菓子屋さんがいい感じ。次々に行動し、前に進んで行きます。こちらにとってもすごく刺激的で、どんどんアイデアが出てきます。そのアイデアを自分たちなりに消化して実行するから、結果も少しずつ出ています。今後がますます楽しみです。
水曜日は化粧品製造販売をしているクライアント様を訪問。マーケティングを中心に数値も見ながら経営の方向性について打ち合わせました。いつも、やるべきことを整理して次への行動を後押ししています。少しずつですが、売上も増えています。真剣勝負で約3時間ぶっ通しのミーティングでした。
午後は、健康食品販売のクライアント企業と新規事業の販売促進の打合せ。ネット戦略の方向性とWEBサイトの内容について。楽天で先行販売していて、そちらで第一号の売上が立ちました。嬉しい!!経営者と喜びを分かち合いました。こちらも3時間半ぶっ通しでミーティング。倒れそうでした。
木曜日は朝から公的仕事をこなした後、夜は起業家の先輩と飲み会。18時前から飲み始め、店を変えて終電まで6時間の濃い時間。いろいろと事業の悩みや今後の話、家族の話などをして、めちゃくちゃ楽しく飲めました。
金曜日は文化の日で子供たちは休み。僕も休み。ただ、朝一のメルマガだけは忘れずに配信。今回で655号目でした。
この日は三重県菰野町のアクアイグニスへ。ここはパティシエの辻口博啓さんのお店があったり、温泉施設があったりする人気スポットで、僕は2回目の訪問。ランチはイタリアンを食べました。美味しくて奥さんも子供たちもニコニコ。その後温泉でゆっくりした後、芝生広場で子供たちとサッカーやったり、奥さんが買ってきたスイーツを食べたり。ここで次男(小1)が急にサッカーに目覚めて、すごくやる気になったんです。今までの興味はゲームばかりだったんで、サッカー好きな僕として、そして親として、とても嬉しい出来事でした。
ただちょっと残念だったのは、美しい山々をバックにした景観の良さがこのアクアイグニスの特長なのに、現在となりで高速道路の建設中で、景観を思いっきりぶち壊してます。これ、かなり残念な状況になるんじゃないかな・・・。経営者は折り込み済みだったのか、それとも誤算だったのか。でも本当に日本人って「景観」に対する意識が低すぎるんじゃないかな。(ウチの近くの鶴舞公園のグランドの周りの美しい桜並木はほとんど引っこ抜かれるし。)
土曜日は、僕の実家に奥さんと子供たちとともに帰って、親の顔を見てきました。変わらず元気で良かったです。
来週は新しい顧客で研修が入っているので、その準備を抜かりなくやらなくては。再来週はレイマッククラブのセミナーもあるので、その準備も。
大変だけど、毎日楽しく仕事して、食べて、飲んで、子供と遊んでます。
【セミナーのお知らせ】———————————————-
11月14日にセミナーを行います。テーマは「あなたのコンサル化」です。
(内容)
モノを売ろうとする姿勢だけが強いと、かえって全く売れないという事態に陥ります。
そうではなく、小さな会社は、顧客が抱えている困りごとやニーズを把握し、その解決をサポートするという姿勢がとても重要です。信頼できる「コンサルタント」となり、顧客の問題解決のために、自分の専門知識と人間性をフル投入していく、というセルフイメージを持つのです。
今回のセミナーは、小さい会社が「コンサルタント」として顧客をサポートするためのスキルや考え方を分かりやすく解説し、すぐに実行に移せるようなアイデアを提供いたします。
【日時】 :2017年11月14日(火) 19時~20時45分(18時半受付開始)
【場所】 :ウインクあいち 904 名古屋市中村区名駅4-4-38
【料金】 :5000円(税込み)レイマッククラブ会員は2000円
※友割あり(ペアで参加されますと、各お客様1000円オフ。但し初参加の方のみ
【定員】 :30名
【懇親会】:あります。予算別途3000円くらいです。
お申込みは→: https://raymac.jp/46thseminar/
2017/11/03
その日のうちに第一歩を ~村上春樹氏に学ぶ
■小説家になったきっかけ
先日、たまたま本屋で村上春樹氏の「職業としての小説家」という本を買いました。
特にファンだったわけでもないし、前から読みたいと思っていたわけでもなく、本当に、たまたま目に止まった、という感じです。
この本には、氏の小説家になったきっかけが書いてありました。
プロ野球のヤクルトスワローズのファンだった村上さんは、ある休みの日、神宮球場の芝生の外野席で、ひとりで野球を見ていたそうです。
そのとき、「その瞬間」がきたのだそうです。
■突然降ってきた
ある選手が二塁打を打ち、ぱらぱらとまばらな拍手が起きたとき。
ふと、「そうだ、僕にも小説が書けるかもしれない」と思ったのだそうです。
何の前触れもなく、突然そう思ったのだそうです。
いわば、天から降ってきた。
そして、それを境に、氏の人生の様相はがらりと変わったのだそうです。
それまで、小説を書いたことも無く、小説家になりたいと思ったこともなく、ただ好きな音楽をかける喫茶店を経営していた氏は、その日から「小説家」になったのです。
■その日のうちに第一歩
もともと才能はあったのだと思います。あれだけの実績を生み出した人ですから。
ただ、僕がなるほど、と思ったのは、氏が「小説が書けるかもしれない」と思った後の行動です。
村上さんは、試合が終わった後、そのまま電車で新宿の紀伊国屋に行って、原稿用紙と万年筆を買ったのだそうです。そして小説を書き始めた。
思い立ったとき、その熱が冷めないうちに、次の行動をしたこと。
僕はここに分かれ目があると思います。
やろうと思ったことを、なかなかやらない人たちがいる(僕も含めて)。自分の中で盛り上がったはずなのに、結局やらないまま歳をとっている。
その原因は、思い立ったその日のうちに第一歩を踏み出さなかったから、なのかもしれません。
■自分レベルの視点で
自分レベルではいかがでしょうか?
あなたは、やろうと思ったことを、明日に引き伸ばし、それが明後日になり、一週間後になり、結局やらなかったという経験がありませんか?
やろうと思ったことを、確実にやるためには、思ったその日にやり始めること。一回寝かせてしまったらダメなんです。
村上春樹さんは、プロ野球を見ながら「小説家になれるかもしれない」と思い、その足で(ここが大切)原稿用紙と万年筆を買い、店が終わってから小説を書き始めました。
そして新人賞を獲り、ベストセラーを生み、作家として大成功しました。
僕たちは、氏の才能は真似できませんが、行動は真似できます。
思いついた勢いでそのまま行動する。せっかくの思いを寝かせない。そうすれば、少し前に進む。
寝かせてしまったら、何も起こりません。
応援しています。
(無料メールマガジン「愛される会社の法則」第604号より)
※メルマガの登録はこちらから。(無料)
【セミナーのお知らせ】———————————————-
11月14日にセミナーを行います。テーマは「あなたのコンサル化」です。
(内容)
モノを売ろうとする姿勢だけが強いと、かえって全く売れないという事態に陥ります。
そうではなく、小さな会社は、顧客が抱えている困りごとやニーズを把握し、その解決をサポートするという姿勢がとても重要です。信頼できる「コンサルタント」となり、顧客の問題解決のために、自分の専門知識と人間性をフル投入していく、というセルフイメージを持つのです。
今回のセミナーは、小さい会社が「コンサルタント」として顧客をサポートするためのスキルや考え方を分かりやすく解説し、すぐに実行に移せるようなアイデアを提供いたします。
【日時】 :2017年11月14日(火) 19時~20時45分(18時半受付開始)
【場所】 :ウインクあいち 904 名古屋市中村区名駅4-4-38
【料金】 :5000円(税込み)レイマッククラブ会員は2000円
※友割あり(ペアで参加されますと、各お客様1000円オフ。但し初参加の方のみ
【定員】 :30名
【懇親会】:あります。予算別途3000円くらいです。
お申込みは→: https://raymac.jp/46thseminar/
2017/11/01
リッツで1人アフタヌーンティする男
愛知県名古屋市で中小企業のNew(新しいチャレンジ)を支援する経営コンサルティング事務所、レイマックの豊田礼人です。
仕事をする男性たちが1人の時間を大切にしている、という記事が日経MJに掲載されていました。(2017年11月1日号)
例えば、ある20代の会社員は、終業後に遊園地に行き、1人で大観覧車に乗る。1周13分は、日々の業務から離れ、自分の考えをまとめる時間なのだそうです。またある30代の男性は、リッツやマンダリンオリエンタルなどの高級ホテルで、1人きりのアフタヌーンティを楽しむのだそうです。ホテルによっては1杯3900円とかするものの、仕事上のヒントを得る時間として利用しているのだとか。
僕も1人で過ごす時間は好きで、1人で飲みに行ったり、1人で回転ずし行ったり、1人でバイキングに行くこともあります(笑)。←基本、“飲み食い”ですね。
「仕事で一杯になった頭を整理する」という意味では、週4~5回の夜ウォーキング&ランが僕にとってのその時間。じっとしている時よりも、動いている時の方が考えが整理されやすい気がします。また夜だから、目からの視覚情報が入りにくいというのも、集中するのに良いのです。あと、週1回プールで1時間くらい泳ぐのですが、泳いでいる時も脳みそが開放され、やるべきことなどを整理するのにいいですね。これまた水の中は水しか見えないが良いのかもしれません。
こういう話になると、1人の時間を持ったり、あるいは旅行したりスポーツしたり飲みに行ったり、とにかく仕事から一旦離れることでリフレッシュして、気持ちを切り替えることが重要ですよ、みたいな話になるんですけど、
結局、仕事でたまったモヤモヤを晴らすためには、「仕事で達成する」しかないんじゃないないかな、と僕は思っています。
いくら飲みに行って騒いでも、スポーツや旅行で楽しんでも、ごまかすことはできても、モヤモヤは晴れないですもんね。仕事に戻れば、元の木阿弥。すぐ戻ってしまう。
仕事の問題は、仕事で晴らすしかないよな、と思います。仕事で晴らすとは、目標を達成することです。達成すれば、めちゃくちゃスッキリしますもんね。これ以上のスッキリ方法はない。だから自分でやるしかないんですよね。誰かに相談して多少スッキリするかもしれませんが、やるのは自分。自分の目標を達成してくれる人は、自分以外にいないですもんね。
一番のストレス解消法は、「達成」です。
達成するために、1人の時間を上手く使って、頭を整理したりアイデアを出したりするのが良いですよね。
あとは、楽しむことかな♪
さあ、達成して、スッキリしよう!
【セミナーのお知らせ】———————————————-
11月14日にセミナーを行います。テーマは「あなたのコンサル化」です。
(内容)
モノを売ろうとする姿勢だけが強いと、かえって全く売れないという事態に陥ります。
そうではなく、小さな会社は、顧客が抱えている困りごとやニーズを把握し、その解決をサポートするという姿勢がとても重要です。信頼できる「コンサルタント」となり、顧客の問題解決のために、自分の専門知識と人間性をフル投入していく、というセルフイメージを持つのです。
今回のセミナーは、小さい会社が「コンサルタント」として顧客をサポートするためのスキルや考え方を分かりやすく解説し、すぐに実行に移せるようなアイデアを提供いたします。
【日時】 :2017年11月14日(火) 19時~20時45分(18時半受付開始)
【場所】 :ウインクあいち 904 名古屋市中村区名駅4-4-38
【料金】 :5000円(税込み)レイマッククラブ会員は2000円
※友割あり(ペアで参加されますと、各お客様1000円オフ。但し初参加の方のみ
【定員】 :30名
【懇親会】:あります。予算別途3000円くらいです。
お申込みは→: https://raymac.jp/46thseminar/
最近のブログentries
コンサルプランconsulting plan
情報発信information