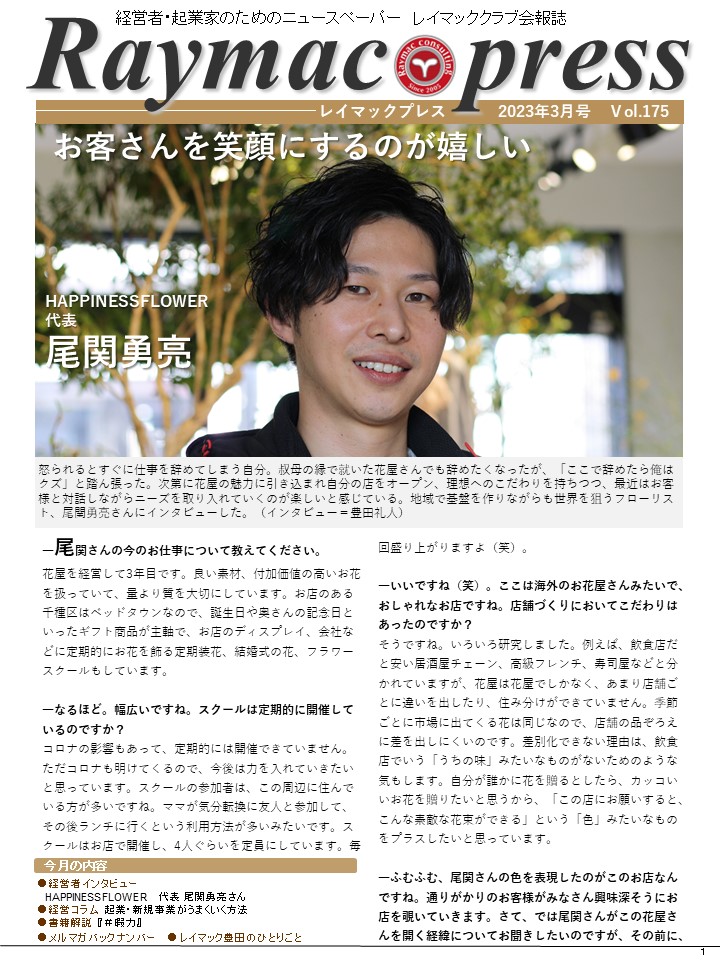2025/11/19
携帯電話に見知らぬ番号から電話がありました。恐る恐る出てみると・・・
今日は寒かったですね。愛知県名古屋市で中小企業の業績アップを親身に支援する経営コンサルティング事務所、レイマック・コンサルティングの豊田礼人です。
午前中は、自動車関連のクライアント様での定期ミーティング。1か月を振り返り、懸案事項の整理をしつつ、来月以降の取り組みについて経営者と社員さんとディスカッションしました。
社長がハンドドリップでコーヒーを淹れてくれたので、淹れたての香りを楽しみながら、リラックスした良いミーティングができました。ここ数か月、オンラインショップである商品の強化をしていたのですがその商品が今月ポンポンポンと売れて、ちょっと光が見えました。検索順位も上がってトップ表示されるようになり、ちょっと皆で喜びました。今後が楽しみです。

打合せ後、携帯電話に見知らぬ番号から電話がありました。恐る恐る出てみると、昨日会った、別のクライアント企業の社長でした。いつも電話してくるのは専務さんの方だから「何か、緊急事態かな?」と身構えましたが、聞いてみると、忘年会へのお誘いでした。
もちろん、よろこんで笑。
クラアイント様にこうやって飲み会や社員旅行に誘われるのは、コンサル冥利に尽きます。仲間として受け入れられているという感じがして、とても嬉しく思います。
楽しみです。
しかし一方で、こうした突然の電話には、少しだけドキッとする瞬間もあります。
こうやって、いつもと違う感じで突然クライアントから電話があると、ちょっとびっくりするのは、仕事が終わる時って、こうやって突然電話で告げられることが、時々あるんですね笑。まあ、独立して仕事をしていると、常に「今日で最後かもしれない」と思って仕事をしているので、それなりの覚悟はしているつもりですが、やはり背筋がピッと伸びる感じがしますね。
いつも、崖っぷちにいる気持ちでベストを尽くそうと肝に銘じています。
僕の仕事とは、経営者や社員さんと課題を共有し、次の一手を一緒に考え、成果につなげるべく伴走することです。売上が伸びた瞬間を共に喜び、時に突然の連絡に身が引き締まる。それでも常に「今日で最後かもしれない」という覚悟で、崖っぷちに立つような気持ちで信頼に応え続けることだと感じています。
今日もお疲れさまでした。
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――
★売上アップに役立つ小冊子
「売るため7(セブン」【ダウンロード版(無料)】
ダウンロードはこちらからどうぞ。
売るために必要な7項目について、ひとつずつ丁寧に解説しています。
7項目を整理するために役立つ「ウルタメシート」付き。


【紙で読みたいという人へ】
★売るため7(ウルタメセブン)【冊子版(有料)】(123頁)
ご購入はこちらから。
2025/11/15
クライアント企業の60周年記念パーティに参加しました
今日は休日でしたが、クライアント企業の60周年記念パーティに参加しました。
こちらの企業様とはかれこれ12年ほどのお付き合いです。長い間、お世話になっています。
名古屋市内のホテルで盛大に行われました。たくさんの料理、お酒、デザートでお腹も満たされ、ビンゴ大会では地元のタレントさんも登場し、楽しく、盛り上がりました。特にデザートが充実していて、僕もたくさん頂いちゃいました。
会場では創業社長が率いたころからの写真がスライドで紹介され、それを見ながら「この60年の一部に自分も関われていたのか」と思うと、感慨深いものがありました。
また、いつもお世話になっている方々、久しぶりに会った方々といろいろと話し、親交を深めることもできたのが何より嬉しかったです。
パーティ後は、昔からお世話になっている方と場所を変えて飲み直し。昼間からビールと酎ハイという背徳感を共有しながら笑、最近の仕事の話やお互いのプライベートのことなどを話しました。それにしても昼間の3時ごろでしたが、その飲み屋さんがお客さんで満席だったのがおもしろかったです。
次は70周年を目指し、できうる限り、サポートしていければと、意を固くしております。
僕の仕事とは、クライアント企業の成長や節目に寄り添い、長期的な信頼関係を築くことです。周年記念などの節目に参加して喜びや思い出を共有しながら、企業の歴史や人に触れ、次の成長をサポートする役割を担うことだと感じています。
今日も、お疲れさまでした。
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――
★売上アップに役立つ小冊子
「売るため7(セブン」【ダウンロード版(無料)】
ダウンロードはこちらからどうぞ。
売るために必要な7項目について、ひとつずつ丁寧に解説しています。
7項目を整理するために役立つ「ウルタメシート」付き。


【紙で読みたいという人へ】
★売るため7(ウルタメセブン)【冊子版(有料)】(123頁)
ご購入はこちらから。
2025/11/06
計画に命を吹き込むのは人間、経営を動かすのは、正解ではなく情熱である
愛知県名古屋市で中小企業の業績アップを支援している、レイマック・コンサルティングの豊田です。
今日は2週間前の打合せをもとに、経営計画をさらに詰めるため、クライアントの社長とディスカッションしました。
前回のヒアリング後、僕なりにあれこれ思考を巡らせました。歩きながら、温泉に浸かりながら、本を読みながら──社長の言葉を思い返し、他社の事例や最近の経営トレンドを頭の中で組み合わせていく。そうして一つのコンセプトにまとまったところで、AIと壁打ちし、A4シートに落とし込みました。
さて、今日の社長は、なぜか前回とは違って晴れやかなエネルギーに満ちている感じがします。この2週間で、あちこち出かけて、多くの人と会い、考えを深めたようで、自分の中で方向性が明確になったようです。
結果的に、僕の提案と社長の考えにズレが生じましたが、それはむしろOK。僕の案は一歩引いて、社長の意思を中心に戦略を組み直しました。最終的に、とても良い方向性が定まりました。
自分のアイデアが採用されるのも嬉しいですが、それ以上に「経営者が納得して腹落ちした戦略」が形になることが、僕にとって一番嬉しいこと。
誰しもいうように、経営は「唯一の正解」が分かりにくいし、やってみなければ分からないことだらけです。だからどんな道を選ぶかよりも、その道を本気で走るエネルギーの大小の方が結果を決める。
だからこそ、僕の役割は、経営者の身体の中からその熱を見つけだし、引き出すこと。「本当にやりたいことは何か」。コーチングし、事例を示し、アイデアを提供して思考を刺激しながら――
経営者の内側から「これで行く」と言える方向性が湧き上がるまで伴走する。
計画に命を吹き込むのは人間である。
経営を動かすのは、正解ではなく情熱である。ちょっと青臭いですが、これ、結構真実を突いていると思います。
僕の仕事とは?
経営者の内にある情熱の火を見つけ出し、それを戦略という形に変えること。正解を押しつけるのではなく、「これで行く」と腹から言える道を共に描き、計画に命を吹き込むこと。
今日もお疲れさまでした。
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――
★売上アップに役立つ小冊子
「売るため7(セブン」【ダウンロード版(無料)】
ダウンロードはこちらからどうぞ。
売るために必要な7項目について、ひとつずつ丁寧に解説しています。
7項目を整理するために役立つ「ウルタメシート」付き。


【紙で読みたいという人へ】
★売るため7(ウルタメセブン)【冊子版(有料)】(123頁)
ご購入はこちらから。
2025/10/30
自社において、競合他社を圧倒的に上まわるレベルの能力とは何か?
月曜日の朝がつらいのは、何年たっても変わりません。こんにちは。愛知県名古屋市で中小企業の業績アップを親身に支援する経営コンサルティング事務所、レイマック・コンサルティングの豊田礼人です。
今日の午前中は、クライアントに訪問し、月に一度の定期ミーティング。
社長から現在の状況は懸案事項を聞かせてもらい、二人でブレストでアイデアを出し合ったり、深くディスカッションしたりしました。テーマは、自社の強みは何か、コア・コンピタンスは何か。それらを活かして、今後どのように資源配分し、事業展開していけば良いか、について。すぐに答えが出る問いではありませんが、何度でも議論し、解を探究しています。
ちなみにコアコンピタンス(Core competence)とは、ある企業の活動分野において、 「競合他社を圧倒的に上まわるレベルの能力」「競合他社に真似できない核となる能力」の事を指します。単なる強みではなく、市場においてサバイブし、成長するための能力のことだと理解するのが分かりやすいと思います。
Wikipediaによると、この理論はゲイリー・ハメルとプラハラードがハーバード・ビジネス・レビュー Vol.68(1990年)で提唱したことで知られるようになったそうです。両氏の定義によると、コア・コンピタンスは次の3つの条件を満たす自社能力のことだとしています。
・顧客に何らかの利益をもたらす自社能力
・競合相手に真似されにくい自社能力
・複数の商品・市場に推進できる自社能力
長年の企業活動により蓄積された他社と差別化できる、または競争力の中核となる企業独自のノウハウや技術のことで、これに該当する技術には、「様々な市場に展開可能」「競合他社による模倣が困難」「顧客価値の向上に大きく寄与する」等の共通性質を持っている、とされています。
自社のコアコンピタンスは何か?自社において、競合他社を圧倒的に上まわるレベルの能力とは何か?それを見つけ出し、強化していくための具体的な方法は?
これからも各クライアントと膝を詰めて議論し、探求の旅を続けていきます。
午後からは、新規のお客様と新プロジェクトについてのオンラインミーティング。
僕の仕事とは、クライアントと共に自社の核となる強み=コア・コンピタンスを見つけ出し、それを磨き上げて事業の成長へとつなげていくこと。
今日もお疲れさまでした。
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――
★売上アップに役立つ小冊子
「売るため7(セブン」【ダウンロード版(無料)】
ダウンロードはこちらからどうぞ。
売るために必要な7項目について、ひとつずつ丁寧に解説しています。
7項目を整理するために役立つ「ウルタメシート」付き。


【紙で読みたいという人へ】
★売るため7(ウルタメセブン)【冊子版(有料)】(123頁)
ご購入はこちらから。
2025/10/24
僕のコンサル独立日記(5)~商工会議所への飛び込み訪問は門前払いの嵐~
コンサル独立日記(4)から続く。
独立してすぐに大きめのコンサル契約を獲得することができ、それなりに収入は得ていましたが、「この契約が切れたらどうしよう?」という不安は常にあり、もっと顧客を増やさなければいけないと思っていました。
それで、商工会議所に行ってみることにしました。商工会議所をはじめとする公的な中小企業支援機関には僕のような中小企業診断士が行う仕事がたくさんあるのではないか、と信じ込んでいたんです。資格さえ取れば、仕事がすぐに来るのだと甘く考えていました。
まず、地元であり愛知県内で最も大きな会議所である名古屋商工会議所を訪問しました。コネは無いので、飛び込み訪問です。要件を伝えて待っていると、男性職員さんが近づいてきて、「中小企業診断士として登録している先生方はたくさんいます。あなたも登録はできますが、仕事が回ってくることは、恐らく難しいでしょう」と言いました。
仕事がありそうな商工会議所には、ベテランの先生たちが列をなしていて、仕事にありつくためには、列の最後尾に並んで待つか、ベテラン先生のカバン持ちになり、おこぼれをもらうしかありませんよ、ということです。これはショックでした。
郊外の商工会議所であれば、もう少し希望があるかもしれないと思い、尾張地区(愛知県の北の方)・三河地区(同南の方)の計10か所くらいの商工会議所に、飛び込み訪問してみましたが、全滅でした。僕は明らかに「招かれざる客」で、職員さんたちはみな、事務的に、お断りの言葉を僕に投げました。
診断士の資格さえ取れば、公的な中小企業支援の仕事なんて、わけなく獲得できると思い込んでいた自分の甘さに気づき、愕然としました。
どうしよう?思っていたのと違う・・・。
「ベテラン先生のカバン持ち・・・」。そんなこと、やりたくない。そういうのが嫌だから、会社を辞めて独立したのです。なんでそんなことを?と変なプライドをこじらせていた僕は、公的な仕事はあきらめました。方向転換し、自分のマーケティング力を磨き、民間企業のコンサル契約をさらに増やしていくことに集中することにしました。
そもそも、僕が始めたのは「中小企業向けのコンサルティングビジネス」です。中小企業が抱える問題を解決し、発展の支援をする仕事です。中小企業が一番解決したい問題とは、「売上を増やすこと」です。この売上の問題を解決しますよ、と言っているコンサルタントが、自分の売上を上げられないようでは、笑い話だし、とても不誠実なことだな、と思いました。
「自分ではできていないことを教えますよ」、と言っているわけだから、お前が言うな、と言われます。これを不誠実と呼ばずに、何を不誠実と言うのだろうか?と思ったのです。
それで、ホームページをさらにブラッシュアップし、メールマガジンは引き続き毎週発行、読者増加のための広告宣伝、マーケティングや経営戦略について自分の考えをまとめた小冊子の作成・配布、ニュースレターの毎月発行などに時間とお金を投入し続ける作戦に切り替えたのです。売上向上策の実践に次ぐ実践です。
これによって民間企業のクライアントは増え始め、収入も安定してきました。今振り返って何よりも良かったのは、自分のマーケティングをしっかりと考えて実行したことで、「実践から得た生きたノウハウ」が手に入ったことです。これが本当にその後の自分を助けてくれました。
飛び込み訪問した時に断ってくれた公的機関の人たちに、感謝しなければなりません。(嫌味じゃなく)もし、すぐに仕事を得て、それなりに忙しくなってしまい、中途半端に収入を得て、何となく安定してしまっていたら、自分で実践して仕事を得るという経験を経ずにいたかもしれません。怪我の功名ですよね。
そして、民間企業と直接契約してコンサルティングを実践し、コンサルタントとしての経験値も増えてきたころ、いつもお世話になっていた税理士であり中小企業診断士でもあったN先生に声をかけられました。
「豊田さん、〇〇商工会議所を紹介してあげるから、一緒に行こう」
言われるままにN先生と一緒に訪問すると、初対面の担当者さんが手に契約書を持って出て来て、名刺交換するや否や、その契約書を机に広げました。
それは年間〇百万円くらいのプロジェクトの契約書で、すでに私の名前が入っていました。担当者さんは「N先生の紹介だから、もう豊田さんに決めました。ここにハンコ、押してください」と言いました。自分をアピールすることも、プレゼンすることもなく、仕事が決まっていました。
飛び込み訪問では門前払いの嵐だったけど、信頼ある人からの紹介だと、こんなに簡単に扉は開くのだな、と思った瞬間です。
こうして、民間企業のコンサルティングをしっかりやりながらも、公的機関とのつながりを持ちながら、バランスよく仕事ができる環境が整い始めたのです。
コンサル独立日記(5)終わり。(6)へ続く。(1)から読む。
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――
★売上アップに役立つ小冊子
「売るため7(セブン」【ダウンロード版(無料)】
ダウンロードはこちらからどうぞ。
売るために必要な7項目について、ひとつずつ丁寧に解説しています。
7項目を整理するために役立つ「ウルタメシート」付き。


【紙で読みたいという人へ】
★売るため7(ウルタメセブン)【冊子版(有料)】(123頁)
ご購入はこちらから。
最近のブログentries
コンサルプランconsulting plan
情報発信information